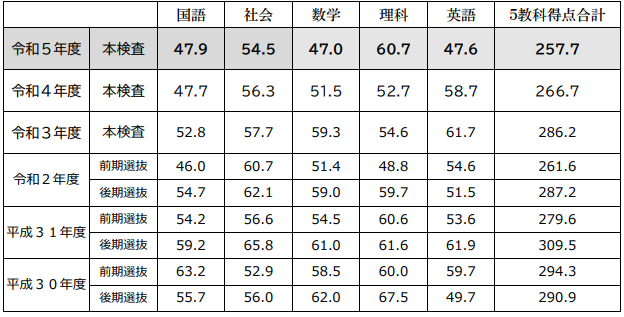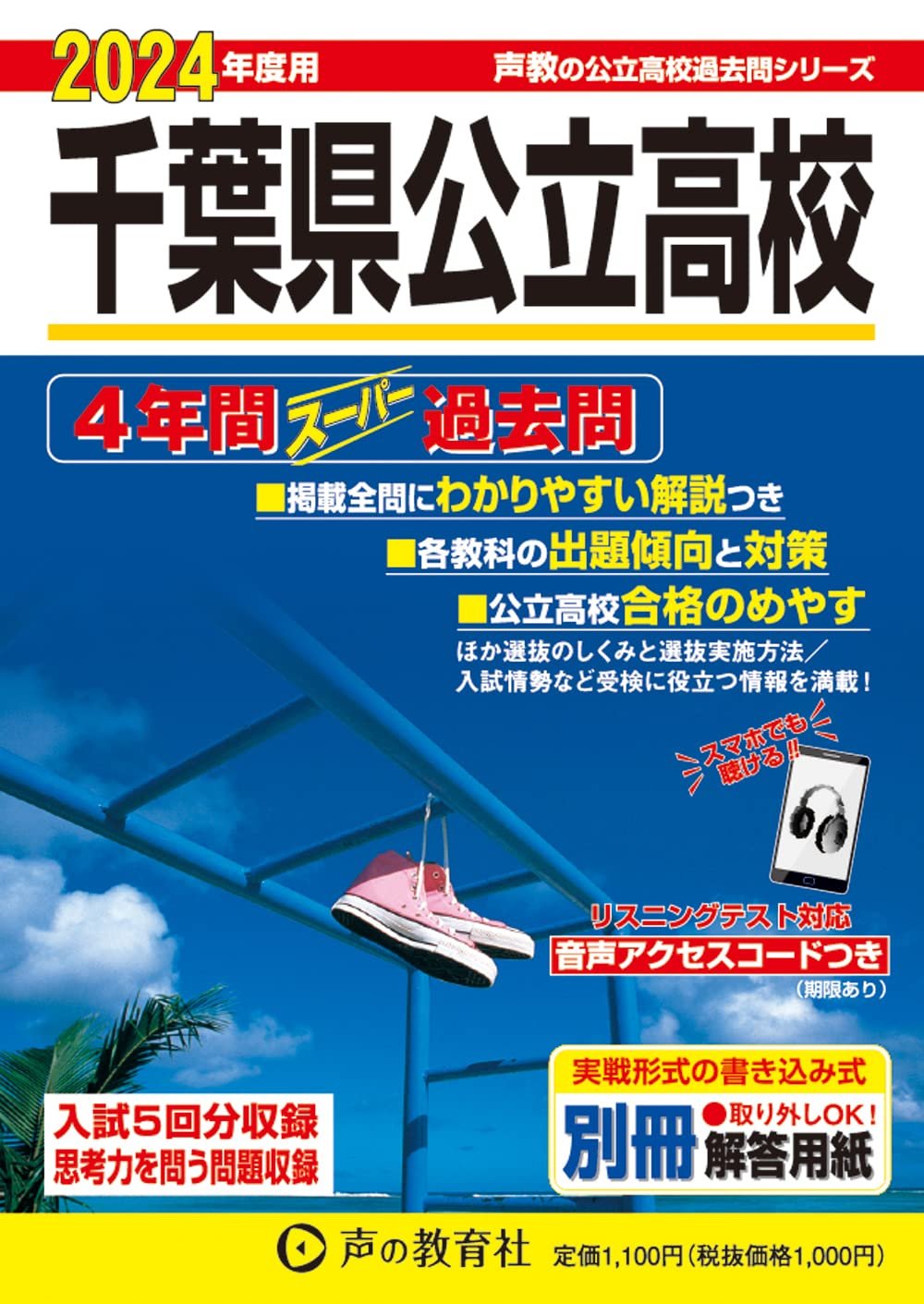2023.10.12

~変わりゆく千葉県公立高校入試 入試傾向 令和6年度(理科)~
理科には、「物理」「化学」「生物」「地学」通称 物化生地(ぶっかせいち)という4分野があります。
千葉県入試では、これらの4分野が同じ割合で出題されています。配点で言うと、4つの分野で25点ずつです。
作図、記述、計算問題の応用的問題も必ず出題されますので、用語を覚えるたけの、いわゆる一問一答式の学習ですと、なかなか得点化出来ないかもしれません。
千葉県の理科ってどんな感じですか?と問われたときにお答えしている内容は以下です。
「数学のようにすっごい難問が出る可能性は低いです。どちらかというと標準的問題が多いです。
たまに・・・これは高校っぽい内容だなというのが出題されますが、平準化してみてい6割ぐらいの平均ではないかと思います」
理科の作図は、必ず出題されます。
レンズとか、力とか、植物の根とか、遺伝とか天気図とか、電流関連とか・・過去問を紐解いていくと、意外と狭い範囲での作図ですので、作戦はたてやすいですね。
あと、ここがポイント!!と言えるのが、恐らくこれは全国の高校入試の問題でもそうでしょうけれど、
「実験に絡んだ問題」です。
いずれも実験内容を考察して、表とかグラフからの読み取り、計算、結果からわかることなど、実験絡みの問題ばかりと入試対策として実施してもいいぐらいです。
学校のワークとか、または塾にお通いでしたら、問題集を使っていますよね。その中から、実験に絡んだものをピックアップして、解いていくといいです。
これは何故かいうと、
実験・観察を通して、結果を考察する力=すなわち、思考力とか判断力を問うという観点で千葉県教育委員会の主旨に合致しやすいのです。
実験とか観察というのは、そこから「なぜそうなったのか?」という理由が見いだされますよね。
これが肝なのです。
記述問題については、4問出題されました。「〇文字以内」という指定があったり、
「~簡潔に書きなさい」という字数制限なしの問題もあります。
毎年の傾向と結果から判断しますと、実験や観察の結果から「考察の記述」という形になったときの正答率が低いです。
上位校合格を狙う生徒さんは、この点も要注意です。
計算を要する問題・・・理科でも多くありますよね。
一昨年は8問、昨年は5問出ています。理科の計算問題というと、化学分野と物理分野が多いですが、地学分野にもありますので、よく練習しておきましょう。
理科計算問題の特徴は、「単位変換が必要」であることが多い点です。
この点はよく注意して意識して解いていくようにしていくといいです。
理科というのは、サイエンスの世界。
実は日常生活にものすごく密接にかかわる内容が理科では出題されやすいのです。
例えば、
地震とか火山が何故出題が多いかわかりますよね。
日本に住む以上、ここは地震列島であり、活火山も111ありますので、火山列島と言っても過言ではありません。
このように考えていくと、なぜ天気が多く出題されるのか?
なぜ遺伝が多く出題されるのか?
なぜ電気分野の出題が、全国で一番多いのか?
なんとなくわかりますよね。
日常生活に密接なつながりがあるからです。
ところで、理科って単元数がとても多いです。
| 問題数 | 配点 | |
| 1年内容 | 10問 | 28点分 |
| 2年内容 | 11問 | 30点分 |
| 3年内容 | 15問 | 42点分 |
上述の通り、4つの分野は25点ずつの出題ですが、学年で見ていくと、
去年はこのような感じの出題となっております。
1~2年内容が58点分(約6割)、3年内容が42点分(約4割)です。
理科は、学習したら学習しただけ、しっかりと点数という形にあらわれてきます。
また、それぞれの単元が数学みたいに フルにリンクするわけではありませんので、
いわゆる、単元をザクッと切った形での学習をしても大勢に影響がありませんので、そういう観点でいうと、得意な分野と不得意な分野を簡単に区分けすることが出来ます。
単元数は多いと言っても、それぞれの単元で学習する内容の基礎から標準を定着させるだけでいいので、戦略はたてやすいです。