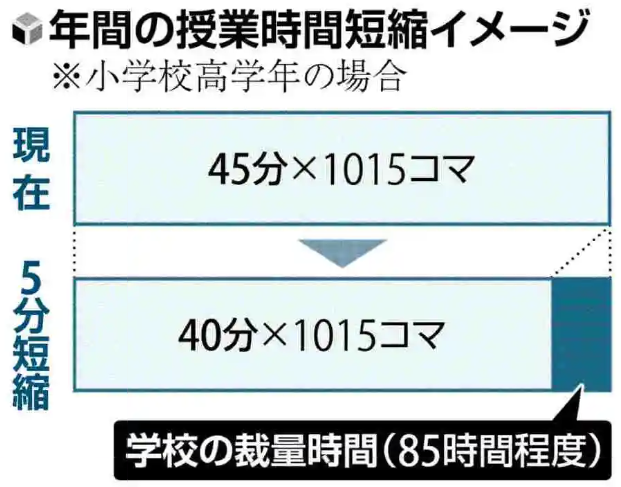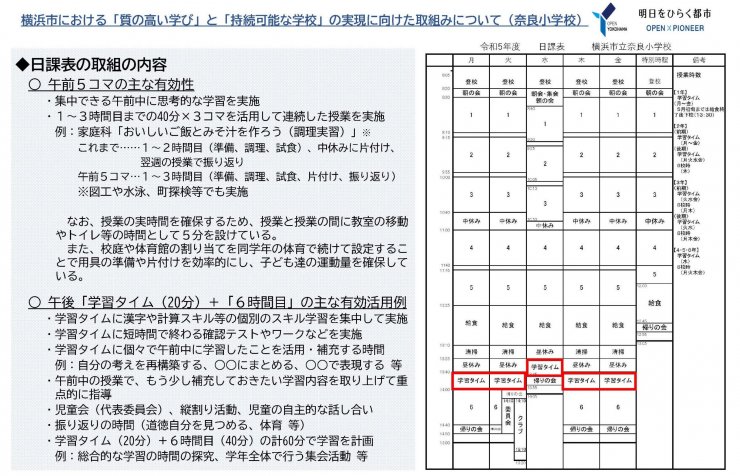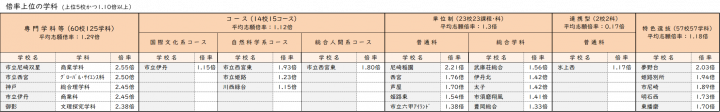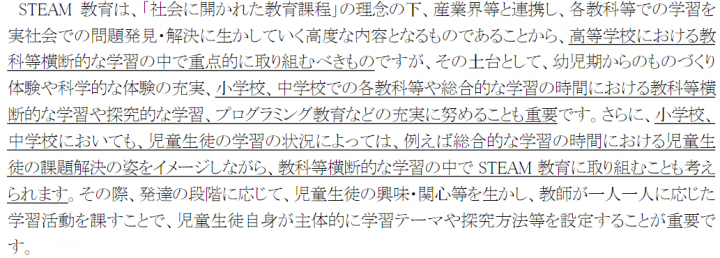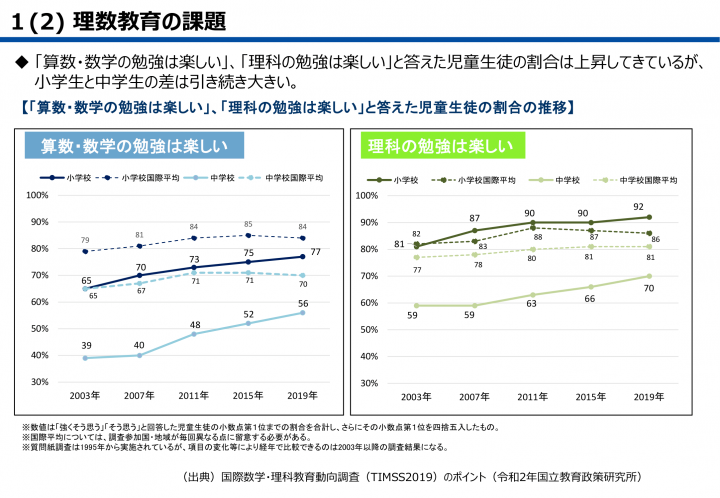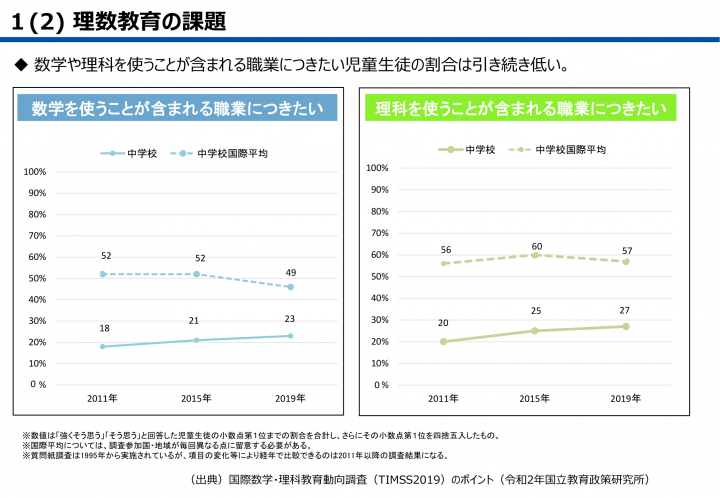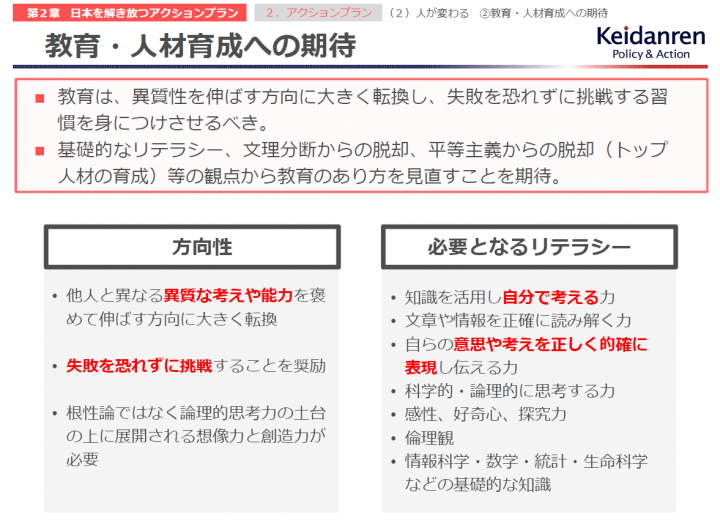2024.02.15
神戸市は、2024年9月から市内在住の高校等の通学定期代を、所得制限を設けずに全額補助すると発表しました。
出典:読売新聞オンライン_2024年2月15日
出典:神戸市長_定例会見(高校生等通学定期券補助の大幅拡充)_20240214
2024年8月末までは、これまで通り60,000円(12,000円ⅹ補助対象期間の月数)を超える通学定期代の2分の1が補助されます。
(参考)
市外の高校等に通う場合の通学定期代はこれまで通り年額144,000円(12,000円ⅹ補助対象期間の月数)を超える通学定期代の2分の1を補助
詳細は決まり次第、ホームページでお知らせがあるようですが、定期券を購入したら、定期券の写真を撮影しておきましょう。
【2023年度までの通学定期券 補助制度】
【補助金の簡易判定】
以下の計算ツールサイトで補助の対象になるか、補助金の交付額がいくらになるか簡易的に算出できます。
神戸市高校生等通学定期券補助計算ツール ← 詳細はコチラから
申請については、原則、e-KOBEで受け付けしています。
通学費の無償化は全国初の事例で、新高校1年生にとっては、心強いサポートです。
神戸市は、高校生の学びを支援する事業が加速しています!
出典:読売新聞オンライン_2024年2月15日
出典:神戸市長_定例会見(高校生等通学定期券補助の大幅拡充)_20240214
2024年8月末までは、これまで通り60,000円(12,000円ⅹ補助対象期間の月数)を超える通学定期代の2分の1が補助されます。
(参考)
市外の高校等に通う場合の通学定期代はこれまで通り年額144,000円(12,000円ⅹ補助対象期間の月数)を超える通学定期代の2分の1を補助
詳細は決まり次第、ホームページでお知らせがあるようですが、定期券を購入したら、定期券の写真を撮影しておきましょう。
【2023年度までの通学定期券 補助制度】
e-KOBEで、撮影した定期券の写真を保管できる画像保管用フォームがあります。(2024年4月1日まで利用可)
定期券画像の保存・送信 ← 詳細はコチラから
【補助金の簡易判定】
以下の計算ツールサイトで補助の対象になるか、補助金の交付額がいくらになるか簡易的に算出できます。
神戸市高校生等通学定期券補助計算ツール ← 詳細はコチラから
申請については、原則、e-KOBEで受け付けしています。
通学費の無償化は全国初の事例で、新高校1年生にとっては、心強いサポートです。
神戸市は、高校生の学びを支援する事業が加速しています!