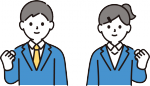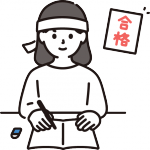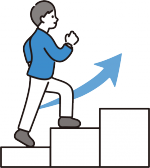2023.11.28
みなさんこんにちは!
城南コベッツ八王子みなみ野教室です。
東京都の多くの公立中学校では2学期期末試験が終わり、中学3年生は仮内申も伝えられている時期だと思います。
みなみ野教室でも、仮内申が発表され、いよいよ受験ラストスパート感が出ております。
仮内申が発表されたことで、都立推薦入試を受験しようとする方もいるのではないでしょうか?
都立推薦入試では、内申点、小論文と面接(今年度は一部高校で集団討論が復活します。)によって合否が決まります。
小学校、中学校で作文は書いてきても、小論文を書いてきた人は少ないのではないでしょうか?
今回は小論文のポイントについてお伝えしていきます。
中学3年生はもちろんのこと、中学1年生、中学2年生にとっても有益な知識になりますので、最後までお付き合い下さい。
1.作文と小論文の違いは?
作文と小論文は共通点がありつつも、いくつかの違いがあります。
以下は、それぞれの特徴と違いについての説明です。
作文の特徴:
①自由度が高い
作文は一般的にテーマが与えられ、その中で自由に表現することが期待されます。
作者の感情や体験、想像力が発揮されることが一般的です。
②文体の自由度が高い
散文や詩、物語など、様々な文体で作成することができます。
表現手段に制限がなく、作者が自分のスタイルで表現できます。
③感情や経験の表現
作文はしばしば、作者自身の感情や経験を表現することが求められます。
読者に感動や共感を呼び起こすことが目標とされることもあります。
小論文の特徴:
①テーマに関する論理的な分析
小論文は通常、特定のテーマに対して論理的な分析を行うことが求められます。
主題に対する論拠や論理展開が重視されます。
②客観性が重要
小論文は客観性が重要視される傾向があります。
主観的な感情や経験よりも、客観的な事実や論理的な説明が強調されます。
③論点の明確化
小論文では論点を明確に提示し、それに対して論理的な根拠を用いて説明することが求められます。読者に対して説得力を持たせることが重要です。
簡単に言えば、作文は作者の感情や表現が主体で、自由な形式が取られることが多い一方で、小論文は特定のテーマに対する論理的な分析と客観的な立場が求められ、論拠や論理展開が重要となります。
2.小論文のポイント
さて、それでは実際に小論文を書く際にはどのような点を意識したら良いのでしょうか?
7つのポイントにまとめてみました。
①テーマの明確な理解
小論文の成功の第一歩は、テーマを明確に理解することです。
問題文や指定されたテーマに対して深く考え、キーワードや重要な概念を把握しましょう。
これによって、的確な意見や論点を提示する基盤ができます。
②構成の工夫
小論文は明確な構成が求められます。
典型的な構成は、「序論」「本論」「結論」です。
序論ではテーマの導入や自分の立場を述べ、本論では論点を展開し、結論ではまとめや提言を述べます。
この構成を守りながら、論理的かつ順序良く文章を進めましょう。
③具体例や事実の活用
論文をより説得力のあるものにするためには、具体的な例や事実を挙げることが重要です。
抽象的な論理だけではなく、実際の出来事や経験を交えることで、論文がよりリアルで読み手に訴えるものとなります。
④論理的な展開
小論文は論理的な展開が求められます。
各段落や文のつながりに注意を払い、一貫性を持たせましょう。
段落ごとに主題文や具体例を結びつけ、全体として一つの論理的な流れを作り上げることが重要です。
⑤文章の工夫
単調でない表現やバラエティ豊かな言葉遣いは、読み手の興味を引きます。
同じ表現を繰り返さず、様々な言葉を使うことで、文章全体が魅力的になります。
⑥文章の適切な長さ
指定された字数内で適切な内容を表現することも大切です。
あまりにも短すぎても、長すぎても伝えたいことがわかりにくくなります。
字数制限に合わせつつ、要点をしっかりと伝える工夫が必要です。
⑦校正と修正 最後に、書き上げた論文は時間をかけて校正しましょう。
文法や表現の誤り、不明瞭な部分を見つけて修正することで、論文全体のクオリティを向上させることができます。
以上が小論文の書き方と受験での成功のポイントです。
これらのステップを踏んで、テーマに対する深い理解と論理的な展開を心がければ、高い評価を得ることができるでしょう。
3.日常でのトレーニング
小論文は一朝一夕で書けるようなものではありません。
以下では受験に向けて行うべきことをお伝えいたします。
①過去のテーマで小論文を書く
東京都のホームページ(推薦入試テーマ一覧)にて、年度ごとに実施された内容が公開されております。
こちらから、受験校の過去のテーマにそって書いてみると良いでしょう。
その際、学校や塾の国語の先生に添削をお願いしましょう。
②日頃のニュースに対して意見を述べる
毎日のニュースで報道される出来事に関して、自分なりの考え、意見を親御さんに伝えてみましょう。
この際、主観的ではなく客観的、論理的に意見を述べることを心がけましょう。
こちらは実際に私が実践していたことです。小論文を書く際の意識づけにもなりますし、面接試験の時に自分の意見を伝える訓練にもなります。
都立推薦入試までは、あと60日です。
小論文は最低でも週に1つは書いていきましょう。
---------------------------------------------------------------------------------------------
城南コベッツ八王子みなみ野教室では、小論文対策・面接対策も実施しております。
国語専任、大手IT企業で研修講師も務めてきた教室長自ら指導しております。
国語が不安という小学生、中学生、高校生、受験での小論文や面接に不安があるという方は、
ぜひ一度校舎にお越しください!
校舎見学、学習相談のお申し込み
※確認後、翌営業日以内に八王子みなみ野教室よりご連絡いたします。
【城南コベッツ八王子みなみ野教室】
東京都八王子市みなみ野3丁目2-13 KEN BRIDGEビル1F
※山梨中央銀行みなみ野シティ支店様が目印です。
受付時間:月〜土 15:00-20:00
TEL:042-632-5771
Mail:covez_minamino@johnan.co.jp
---------------------------------------------------------------------------------------------