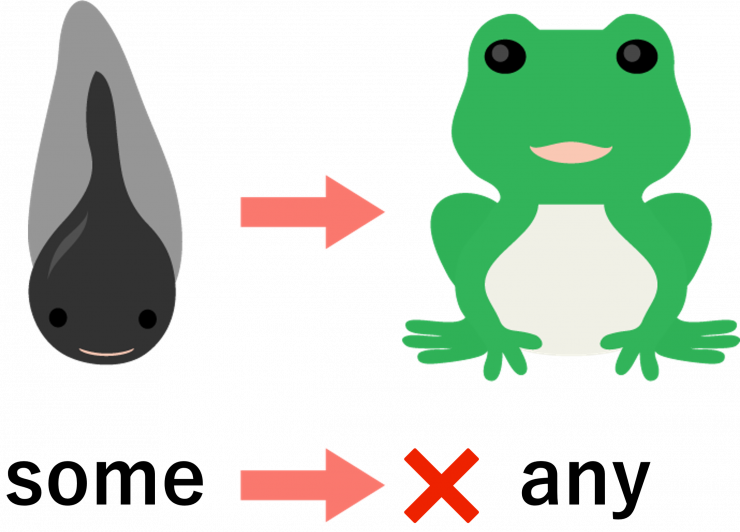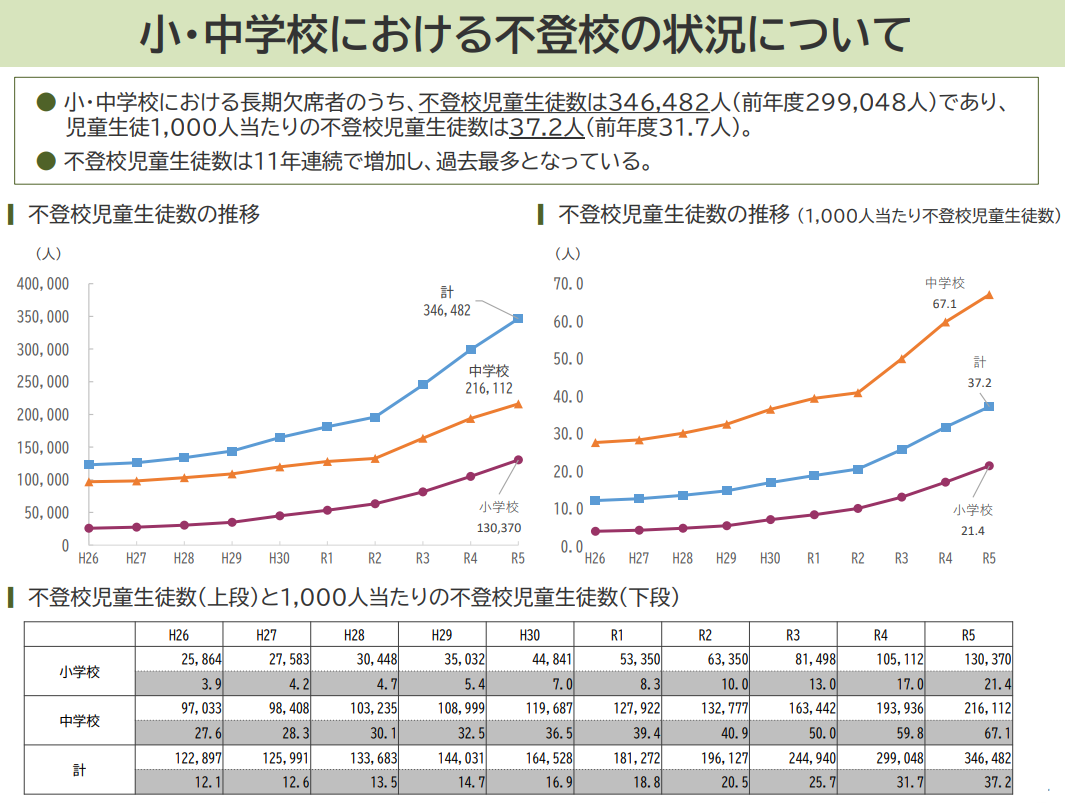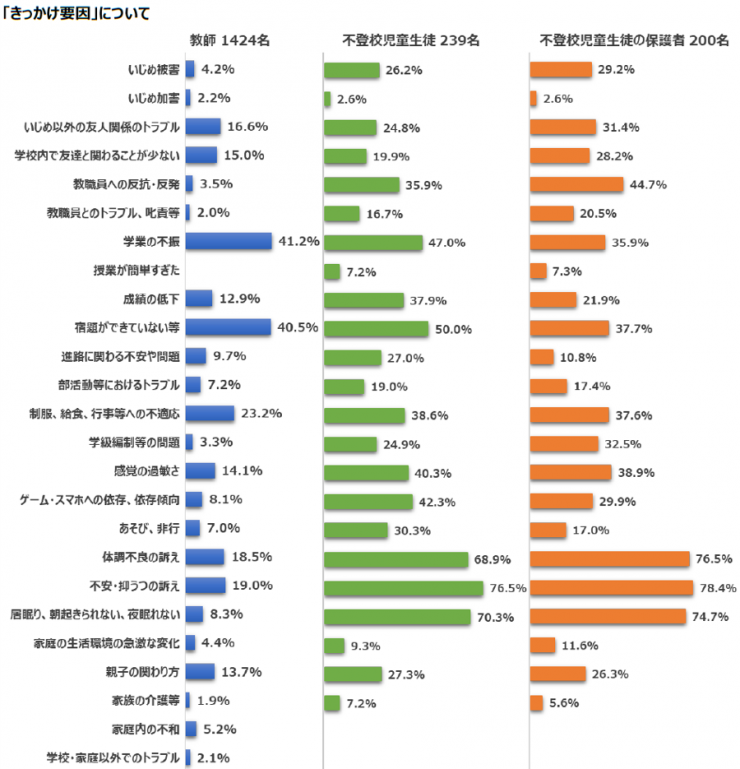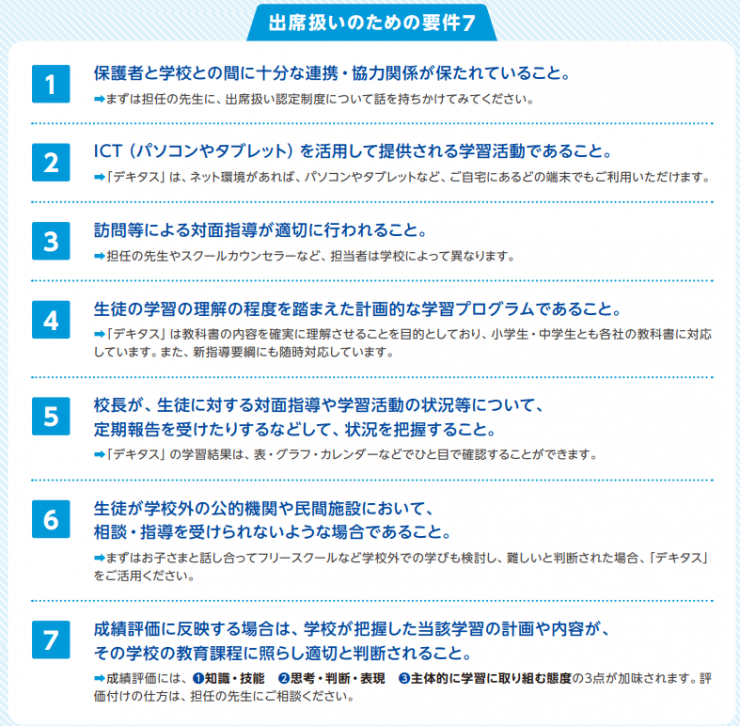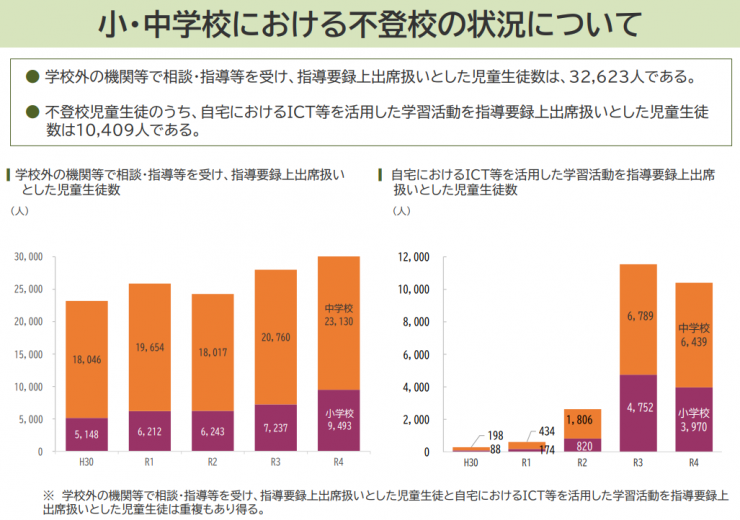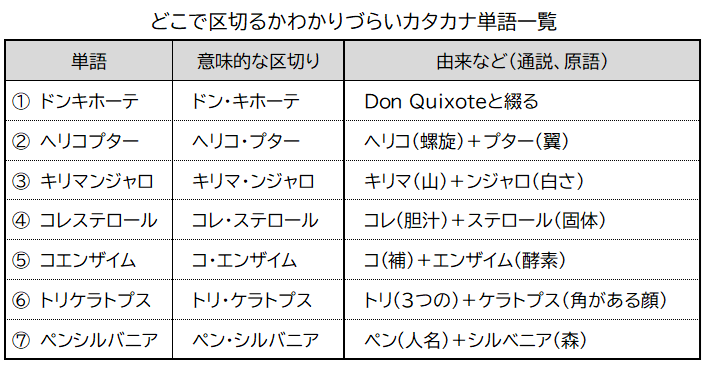2024.12.05
「宿題」は、学校で教わった内容の復習が中心で、繰り返し問題を解くことで理解がさらに深まります。学習した内容を忘れないようにするためには非常に有効な手段です。さらに、学校から帰宅後に宿題をすることで、机に向かうという習慣にもなります。
しかし、やり方を間違うとまったく意味のないものになってしまいます。例えば、学習した内容を理解せずに、適当に解答を記入することで、「宿題は終わった」と勘違いしている子どもがいるとします。この子どもは、テストで同様の問題が出題された時に、正答できるでしょうか?
実は、いくつかの統計によると「宿題をしても学力が上がらない」だけではなく「宿題は学力にマイナスの影響を及ぼす可能性がある」とさえ言われています。
また、ある調査では、「宿題が学力向上に効果を与えるのは高校生以上であり、小学生や中学生においては、宿題をどれだけやっても成績が向上するという証拠は見つかっていない」という結果がでています。
出典:小学館_HugKum
そもそも、「宿題に意味はあるのか」という問いに対しては、様々な意見があります。
山形県では、2023年4月から「宿題なし」を宣言した公立小学校学校があります。この小学校では「やらされる勉強ではなく、自分自身で『?』をたくさん見つけて、"考える学び"を目指している」という校長の想いから始まった施策です。この本質は、「宿題がないから勉強しなくていいではなく、これまで以上に自主的に勉強してほしい」ということにあります。
出典:NHK_宿題がない学校
この小学校の生徒は、学校が用意した数種類のプリントの中から、学習したい単元のプリントを自宅に持ち帰ります。これは強制ではなく、学校に提出する必要もありません。
この施策に対しては、当然のことながら保護者から「まったく勉強しなくなった」「学力の低下がひどい」などの反対意見が寄せられたということです。また、保護者だけでなく低学年を担当する教員からも反対意見がでたそうです。
校長は、宿題をなくす理由について、半年間に30回以上、教員が集まる会議の場で説明し、「宿題なし」の施策が始まりました。
山形県の公立小学校の事例は、「宿題」から「自主学習」に切り替えたことで、教師の授業内容や子どもへの向き合い方に変化が出ているということです。ある教師は「教師が一方的に話すのではなく子どもたちが自ら話し、お互いにやりとりすることで課題の答えにたどりついていく。こうした授業の方が教師、子どもの両方ともが面白いし、子どもたちも興味を持っている」という感想を持っておられます。この施策が始まったことで、休み時間や放課後に費やしていた宿題の作成や採点の時間を、授業の準備や子どもたちに目を向けることに費やせるようになったそうです。
出典:NHK_宿題がない学校
「宿題」自体に意味があるかないかではく、それぞれの学習に対する向き合い方で結果は大きく変わってきます。学習習慣が身に付いていない生徒は、「宿題」をしていくことで、しだいに「自主学習」に発展していくこともあります。
「自主学習」では、自分で内容や目標を決めて勉強するので、自律性だけでなく好奇心や向上心も養われていきます。
子どもはいろんなことに興味や関心があります。よく「勉強に集中力が続かない」という声を聞きますが、興味があることなら、時間を忘れて没頭することもあると思います。
当教室では、マイクラの世界を楽しめる「プログラミング」、ゲーム感覚で楽しめる「速読解力講座」など、子どもの興味を引き立てる教材が揃っています。
それぞれ、レベルを達成するごとに賞状がもらえるので、お子様のモチベーションにもつながります。無料体験を行っていますので、ぜひ一度ご相談ください。